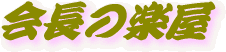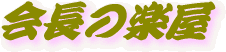今回の開口一番は勘タン君。大きなよく通る声と大きな顔…はどうでもいいのですが、とにかく開口一番にはもってこい。このネタは彼にとっては自家薬籠中でお手のもの。ツボではきちんと笑いを取って高座を下りてきました。これからに向けては面白いところをぐぐっと集約して、15分くらいに短くコンパクトに笑いの取れる勘タン落語に仕上げていけば、更にインパクトのある爆笑高座に仕上がること間違いなし。 |
|

年になって新規一転ということで田楽から改名をした好艶君。うぐいす色の新しい着物も用意してばっちり。ネタは彼にとっては何回も高座にかけている「風呂敷」でした。が、気合が空回りした?のか、本人いわく「久々に落語をやっている最中に『早く高座を下りたい』と思いました」ということ。「好艶」としての次の高座でどう変わるか楽しみです。
|
|

おなじみ酔書の紙切り。他に色物がいないので毎回登場してます(汗;)。さて、鋏試しの「花火」のあとお客様からいただいたお題は「林家三平」と「屋形船」。ちょうど「三平物語」がテレビドラマで放映される日であったので私もお顔を写真で改めて見ていたので助かりました。まあまあの出来ではなかったかと自画自賛。それに」比べ「屋形船は…お客様は正楽師匠の作品のような乙な風情のあるものを期待されていたのでしょうが、できあがったのはまるでベニスのゴンドラ船、、、だから紙切りはやめられない??
|
|

学生時代に覚えたが、最近では高座にかけたことがないと本人が言っていた相撲ネタ。今回、お稽古会を通じて一番お稽古したのは彼ではないでしょうか。台詞を思い出すのもさることながら、台詞と台詞との間を間延びしないようテンポよく会話を進めるようにするのと、身体の線が細いので、相撲(すもん)取りの大きさを出すのに苦労してたようですが、本番ではなかなか落ち着いて中トリの高座を務めました。高校生のお弟子さん?二人も来てくれ、会場設営や撤去に加勢してくれました。感謝です!
|
|
 |
|

「え〜悪気があって出てきたんやおまへんので…」で登場のおなじみ神戸の茆町さん。今回もわざわざ遠方にもかかわらず参加して下さいました。噺は江戸では「だくだく」と呼ばれる泥棒ネタ。相変わらず、表情豊かで愛嬌のある登場人物が出てきて、中入り後のお客さんを落語モードにすぐ引き込むあたりはさすがです!登場人物のばかばかしいやりとりにお客さんは爆笑の渦でした。
|
|

今回は久々の主任(トリ)。会長としてその責任は当然か(笑)。「棒鱈」というネタはこれで高座にかけるのは4回め。しかし、酒飲みの噺は何度やっても難しいとつくづく思います。以前、笑福亭松喬師匠が「酒飲みのネタでは本当に酔っ払ったリアルさを出し過ぎると言葉がお客様に聞き取りにくくなるので、酔っ払った演技をしながらも言葉ははっきり伝えなきゃいけない」ということを言われていたのを思い出します。高座の後半で突然、外で雷の大きな音がしたのにはお客さんも高座の私もびっくりでした。
|
|
|